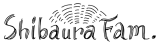目次
ToggleShibaura Fam.のべビスタです。
2025年4月1日と2025年10月1日に育児介護休業法改正が施行されますね(一部を除く)。
子育てをしている世帯や、両親の介護をしている世帯に関わる法律改正です。
今回の法律改正の背景には、共働きの世帯が増えている家庭環境や多様化する家族のニーズに対応し、働き手と家族の両立を支援するための取り組みです。
この法律改正に伴って、具体的にどのような影響があるかご存じでしょうか?
「知っているけど実際どう変わるの?」
「どんな企業、どんな社員が対象になるの?」
「対象になる条件あるの?」
「どんなときの休業が対象になるの?」
と疑問を持っている方もいるのではないでしょうか。
今回は、2025年4月1日から施行される「育児介護休業法等の改正」についてご紹介します。
より詳しい法律の内容や企業での取り組みについては、
厚生労働省HPや地域の行政、お勤めの会社の総務部などにお問い合わせください。
厚生労働省HP
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html

◆育児介護休業法とは
育児介護休業法とは、夫婦共働きの世帯が仕事と育児・介護を両立することを支援する法律であり、働き方改革やライフワークバランスの社会を目指している取り組みです。
夫婦が育児休業を取得しやすい環境を整えることで育児や介護にかかる家庭内の負担を分散することが期待されています。
育児や介護に関する研修の実施、フレックスタイム制度の導入、在宅勤務(テレワーク)の選択肢の拡充などが会社にも求められます。
育児介護休業法等の改正によって、下記のような変更があります。
◆2025年4月1日の改正でどう変わる?
大きな変化ポイントは4つあります。
1、残業免除の対象範囲拡大
2、子の看護等休暇の拡大
3、3歳未満の子を育てる労働者については、努力義務の対象にテレワークを追加
4、育休取得状況の公表義務の拡大
1、残業免除の対象範囲拡大
3歳以上小学校就学前の子どもも対象になります。
所定労働時間を超える労働(=残業)が免除されます。
原則として事業主に対する請求を行うことができるのですが、その所定外労働の制限(残業免除)の対象年齢に改正があります。
<改正前>
3歳になるまでの子どもを育てている労働者
<改正後>
小学校就学前の子どもを育てている労働者
2、子の看護等休暇の拡大
行事参加等の場合も取得可能になります。
「看護休暇」とは、怪我や疾病にり患した子どもの世話などを行うことを目的とした休暇です。
対象となる子どもがいる労働者は、1年度あたり5日を限度に看護休暇の取得が認められています。
※対象となる子どもが2人以上いる場合は1年度あたり10日
<改正前>
名称
・「子の看護休暇」
対象となる子
・小学校就学前
取得理由
・予防接種や健康診断
労使協定を結ぶことで除外される労働者
①引き続き雇用された期間が6カ月未満の労働者
②週の所定労働日数が2日以下
<改正後>
名称
・「子の看護等休暇」
対象となる子
・小学校3年生修了まで
取得理由
・感染症に伴う学級閉鎖等が追加
・入園(入学)式、卒業式が追加
労使協定を結ぶことで除外される労働者
①が撤廃
②のみ継続
3、3歳未満の子を育てる労働者については、努力義務の対象にテレワークを追加
事業主には、3歳未満の子を養育する労働者が育児休業をしていない場合に、在宅勤務等(テレワーク)の措置を講ずることが新たに努力義務として課されます(改正法24条2項)。
在宅勤務等の措置を講じなくても罰則等はありませんが、事業主においては積極的に当該措置を講じ、労働者の仕事と育児の両立を助けることが期待されます。
4、育休取得状況の公表義務の拡大
現行法では、常時雇用する労働者の数が1,000人を超える事業主に、毎年1回以上、育児休業の取得状況を公表する義務が課されています。
改正法では、育休取得状況の公表義務の対象が、常時雇用する労働者の数が300人を超える事業主まで拡大されます(改正法22条の2)。
公表義務の範囲拡大に伴い、より幅広い企業において育児休業の取得促進が期待されます。
<改正前>
常時雇用労働者数 1,000人超
<改正後>
常時雇用労働者数 300人超

◆改正以外に導入される新しい制度
従来の育児介護休業制度に加え、新たな制度が導入されます。
育児時間:
育児中の従業員が、1日1時間まで、勤務時間中または勤務時間外に、育児のための時間を取得できる制度です。
これは、急な子供の病気や保育所の休園など、突発的な事態に柔軟に対応できるよう支援するものです。
介護時間:
介護中の従業員が、1日1時間まで、勤務時間中または勤務時間外に、介護のための時間を取得できる制度です。
これは、急な介護が必要になった場合でも、安心して仕事と介護を両立できるよう支援するものです。
介護休業取得時の給付金:
介護休業を取得した際に、給付金の支給制度が導入されます。
介護する家庭の経済的な負担を軽減し、介護休業取得を支援するものです。
◆さいごに

2025年4月1日施行の育児・介護休業法改正は、家族と仕事を両立する社会の実現を目指した施策だと思います。
制度の活用と社会全体の意識改革によって、誰もが安心して働き、家族と過ごすことができる社会に近づいているのかもしれないですね。
それでは今日はこのあたりで。