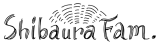目次
ToggleShibaura Fam.のちぃちゃんです。
5月のGWはいかがでしたでしょうか。
お子さんがいる家庭では子どもたちと家でのんびりすることもあれば、家族でおでかけするなどイベントがたくさんあったと思います。
家族団らん、イベントを満喫するのはとてもよいことです。
遠出したご家庭も遠出していないご家庭も子どもにとって楽しい思い出になったのではないでしょうか。
一方で、連休明けは大人だけでなく、子どもは生活リズムを崩しやすい傾向があります。
理由として、環境の変化に敏感なこと、社会的リズム(保育園・幼稚園、学校の時間など)に慣れているため、連休後に反動が出やすくなります。
もしお子さんが生活リズムを崩したときの対処法について、0-2歳児、3-6歳児、7-12歳児別をまとめてみましたのでご参考にしてみてください。

◆0-2歳児への対処法
①起床・就寝時間をまず整える
朝起きる時間を毎日同じにします。
起きたらカーテンを開けて、日光を浴びることで体内時計をリセットし、リズムが戻りやすくなります。
②昼寝のタイミング
昼寝が遅すぎると夜寝つきにくくなるため、午前と午後にそれぞれ30分〜1時間程度に。
昼寝の時間も毎日なるべく同じ時間にしましょう。
③就寝前のルーティンをつくる
「お風呂→ミルク→絵本→お休み」など、毎晩寝る前に同じ流れをルーティン化することで、いつもと同じ時間に入眠しやすくなります。
④寝室の環境を整える
寝室は暗くして静かにすることがおすすめです。
テレビやスマホの音・光は控えましょう。
入眠時は部屋の温度・湿度にも注意が必要です(適温は20〜22℃前後、湿度は50〜60%が目安)。
◆3-6歳児への対処法
①朝の習慣つくり
朝起きる時間と登園準備の流れを“決まったパターン”で動きます。
目覚まし時計をつかう、好きな音楽を流すなど「朝の合図」をつくるとよいです。
駄々をこねていても好きな音楽を聞くと素直に動いてくれやすくなるそうです。
②昼間にしっかり体を動かす
午後に外で遊ぶ時間を確保すると、夜の寝つきがよくなります。
保育園、幼稚園では全力で遊んでもらいましょう。
③テレビ・タブレットは夕方までに
寝る前の2時間はなるべく画面を見せないようにします。
脳が刺激を受け続けると、眠気を感じにくくなってしまうためです。
YouTubeなどの動画は大人が意識して観る時間を管理しましょう。
④「眠る時間が来た」というサインをつくること
歯を磨く、パジャマに着替える、絵本を読む、音楽を流すなど、毎晩決まった“ねんねのルーティン”をつくり作ります。
⑤ 無理に早く寝かせようとしない
リズムを崩していると夜中まで起きてしまう場合もありますが、無理して寝かさないこと。
親のイライラが溜まってしまうと、それが子どもにも伝わって余計に寝付けなくなることがあります。ホットミルクなど温かい飲みものを飲みながら一緒に過ごしましょう。
リズムが昼夜で逆転している場合、昼間の活動量を増やして、夜自然に眠くなるのを待ちましょう。
◆7-12歳児への対処法
①「朝起きる時間」を最優先で固定する
夜寝る時間がずれるのは問題ありません。
朝起きる時間を毎日同じにすることが生活リズムの鍵です。
最初は眠そうにしていても、日中に眠気が出て自然と夜早く眠れるようになります。
②日中の活動を意図的に増やす
外遊び、買い物の手伝い、散歩など、体を動かすことを増やして「夜ちゃんと疲れる状態」にします。
学校に行くようになれば少しずつリズムが戻ります。
③夕方以降は「ゆるやかな時間」に
18時以降夕食後はお風呂→寝る準備をすぐにして刺激の強いこと(ゲーム、動画、激しい運動など)を控える。
どうしても動画を観たい、ゲームがしたい場合は時間を決めること。
④「学校が始まったら困ること」を具体的に話す
小学生は論理的に理解できる年齢なので、
「朝寝坊したら遅刻するよね」
「疲れてると友達と遊んでも楽しくないよ」
といった話を、感情的ではなく“事実”として伝えると納得しやすいです。
◆さいごに
生活リズムは習慣化することで、もとに戻りやすいので、決まったルーティンを試しましょう。
また一番大事なのは親側の態度と姿勢です。
早く寝なさいと怒っても逆効果になりやすく、余計に抵抗して寝ない選択をします。
また子どもは親が夜更かししているところも見ているので真似しますので注意が必要です。
子どもの生活リズムの改善のためには、大人であるわたしたちが早寝早起きの姿勢を見せることが大事です。
以上、子どもの生活リズムが崩れたときの対処法をご紹介させていただきました。
参考になれば幸いです。
それではまた。