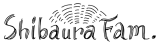目次
ToggleShibaura Fam.のさっちゃんです。
今日2025/10/29から3日間新橋で「全国交流物産展 in 新橋」が開催されます。
そこで、私たちの住む芝浦について改めて調べてみると意外と知らないことがたくさんありました。
今回は芝浦に関するちょっとした豆知識をご紹介します。
◆芝浦は「海の上の街」だった!

現在の芝浦は、実は“東京湾の上に造られた街”なのをご存知でしょうか。
江戸時代の古地図によれば、今のJR田町駅付近まで海が入り込み、「芝浜」と呼ばれる入り江が広がっていました。
当時の海岸線は現在の第一京浜(国道15号)付近にあり、今の街の大部分は明治以降の埋立地です。
漁師がアサリやハゼを獲り、干物を並べる光景も記録に残っています。
明治期以降、東京港の整備事業によって埋め立てが進み、芝浦一丁目から四丁目の土地が造成。
大正から昭和初期にかけてさらに南へ拡張され、港南・お台場に連なる人工島群へと発展しました。
夜の芝浦で潮の匂いがするのは、海が今も運河を通じて内陸まで入り込んでいるからなのだそうです。
地図上では陸でも、「芝浦」はいまも“海とともにある街”なんですね。
◆「芝浦」という地名の語源と起源
「芝浦」という地名は、もともと「芝の浦」――“芝の村の海辺”を意味します。
港区の公式資料によると、文明18年(1486年)に道興准后が著した紀行文『廻国雑記』に「芝の浦」と記されたのが文献上の初出です。
“芝”は草地や浅瀬を指す古語、“浦”は海が陸に入り込む場所のこと。
つまり「芝の浦」とは“草の茂る入り江”という地形そのままの名前でした。
江戸期の地誌にもこの呼称が登場し、明治以降に「芝浦」として定着したそう。
この地名は、埋め立てによって形を変えながらも、海と共に生きた土地の記憶を今に伝える“東京の原風景の名残”なのだそうです。
◆「芝浜」という名の継承――落語から現代まで

江戸時代、芝浦から芝の浜辺一帯は「芝浜」と呼ばれていました。
古典落語には『芝浜』(三遊亭圓朝作と伝わる)というこの地名を舞台にした人情噺があります。
お話の内容は魚屋の勝五郎が浜で大金入りの財布を拾い、夢と現実の間で改心するというものです。
物語の背景にある“浜辺の労働と庶民の暮らし”は、当時の芝浦の情景を映しています。
また、この「芝浜」という名は、現代文化にも息づいています。
アニメ・映画『映像研には手を出すな!』では、主人公たちが通う学校名が「芝浜高校」。
物語の舞台は人工島や運河に囲まれた都市で、水辺や高架構造など港湾エリアを想起させる風景が特徴です。
公式に芝浦をモデルと明言されてはいませんが、湾岸都市の雰囲気はどこか芝浦を思わせます。
さらに2022年開校の港区立芝浜小学校では、地域の旧地名が校名として受け継がれました。
地名は地図から消えても、物語と教育の中で“芝浜”の名は生き続けています。
◆芝浦は“日本のプロ野球発祥の地”だった!?
芝浦には、かつて日本で最初期に職業野球が行われた球場がありました。
大正10年(1921年)、この地に建設された芝浦球場を拠点に、日本運動協会(通称「芝浦協会」)が活動を開始。
選手が報酬を得て試合を行った、日本最初期の職業野球チームのひとつなのです。
球場は木造スタンドを備えた約6,000人収容の本格施設で、東京湾岸の新しい娯楽として賑わいました。
しかし関東大震災(1923年)で被災し、短い歴史を閉じます。
現在、港区海岸3丁目には「芝浦球場跡地――日本初期のプロ野球チーム発祥の地」と刻まれた記念碑が建ち、静かに当時を伝えています。
倉庫と運河の間に、かつて“日本野球の出発点”があった。芝浦は、文化もスポーツも生み出してきた街なのです。
◆まとめ
いかがでしたでしょうか。
調べてみると「芝浦」の歴史には知らないことがたくさんありました。
特にプロ野球発祥の地というのは驚きです。
この歴史ある素敵な「芝浦」の街に関わる皆さまにより喜んでいただけるサイトになるよう励んで参ります。
それではまた次回♪